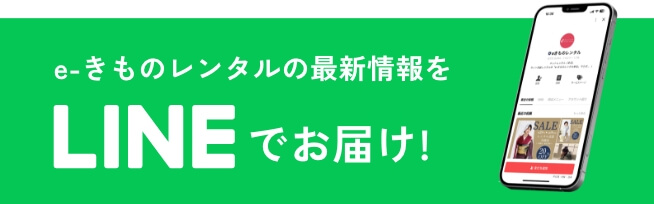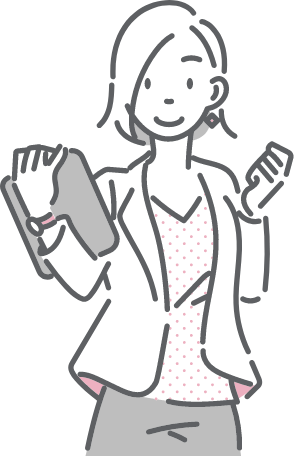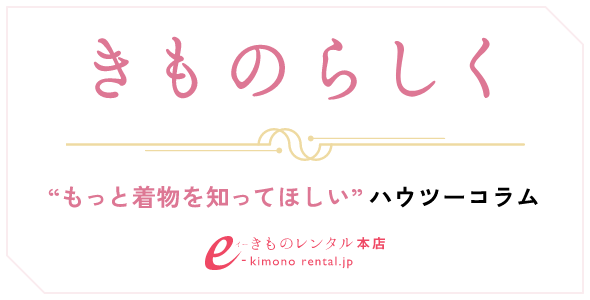
和装結婚式は白無垢で!意味や選び方のポイント・髪型・小物・着付けの基礎知識も詳しく解説

和装結婚式は白無垢で!意味や選び方のポイント・髪型・小物・着付けの基礎知識も詳しく解説
和装で結婚式を行うなら断然、白無垢がおすすめです。
白無垢の歴史は古く、婚礼衣装の中ではもっとも格式が高くて圧倒的気品に満ちています。その魅力に惹かれ、「結婚式をするなら白無垢で!」とお考えの方も多いのではないでしょうか?
今回は、そんな白無垢の特集です。
結婚式で着用する際の基礎知識や選び方や髪型、着付けに必要な小物、また、購入かレンタルがいいかなど詳しく解説します。
白無垢について詳しく知りたい皆様や、婚礼衣装を何にするか決めかねている方も、ぜひ参考にしてくださいね!
白無垢の基礎知識

まず白無垢について基本的なことから解説しましょう。
歴史や魅力、新婦が白無垢の場合の新郎の衣装、さらに同じく和装の婚礼衣装である「色打掛」や「引き振袖」との違いについてもご紹介します。
白無垢とは?歴史と魅力
白無垢は、室町時代から始まったとされる日本の伝統的な婚礼衣装です。全身を白で統一することで、純潔や無垢を象徴し、「嫁ぎ先の色に染まる」という意味も込められています。着物の格式では最高の第一礼装に属し、まさに神聖な儀式にふさわしく、この上なく気品に満ちた衣装ですよ。
後ほど詳しくご紹介しますが、白無垢の際、正式には文金高島田に角隠し、または綿帽子をかぶります。また、他の着物にはない裾の長さであえて床にするように仕立てられているのが大きな特徴です。
普段ではありえない大きくて重みのある髪型に、裾の長さゆえゆったりと歩を進める姿は、花嫁さんの気品と美しさをより一層引き立てます。その様子に参列者からはため息が漏れ、と同時にその目線を釘付けにすること間違いなしですよ。
一生のうちでこのような経験は滅多とないので、新たな人生の門出を祝うに相応しい最高の花嫁コーデといえるでしょう。
白無垢に合う新郎の衣装は?
白無垢に合わせる新郎の衣装は、黒紋付羽織袴(=紋付袴)が一般的です。もっとも格式の高い正装であり、白無垢とのバランスもバッチリですよ。購入の場合、家紋は自身の家のものになりますが、レンタルの場合には「通紋(つうもん)」といって家柄に関係なくどなたでも使用できる家紋が使われています。
近年では、新郎も個性を表現したいというニーズが高まり、紺やグレーといった色物の袴や羽織を選ぶ人も増えています。また、柄物の羽織もあり、かなり斬新ですが、華やかで個性的な雰囲気を演出できますよ。白無垢でもっとも外側に着る白打掛のすぐ下の掛下も基本は白のところ、最近ではそれ以外のカラーや柄の入ったタイプをチョイスする方が増えており、その場合は、新郎も色物や柄物の紋付袴をペアで着用するケースがあります。
色打掛や引き振袖との違い
和装の婚礼衣装には、白無垢の他に「色打掛」や「引き振袖」もあります。
色打掛は、白無垢の一番外に着る白打掛の代わりに華やかで美しくカラフルな打掛を着用します。挙式中に着る方もおられますが、挙式は白無垢にして、披露宴やお色直しで色打掛に着替えるというのが一般的です。元々は白無垢の方が格上でしたが、現代では同等に扱われるようになりました。
引き振袖は、成人式の振袖と違っておはしょりを作らず、裾を長くして引きずるように着るのが特徴です。格式としては、白無垢や色打掛と同様で、最高ランクになります。
成人式で着用される振袖は、一般的に中振袖といって袖が95cm前後です。
それに対して、引き振袖は、大振袖になり、振袖の長さが115cm以上もあります。裾には「ふき綿」が入っており、裾のラインが美しく豪華に見える工夫がされています。
引き振袖は、披露宴や前撮りで着用されるケースが多いですよ。
白無垢を着用する挙式スタイル
白無垢を着用するのは、神前式と仏前式、人前式の結婚式が基本です。
それぞれのスタイルについて解説しましょう。
神前式

神社で行われる神前式は、神道の伝統的な儀式にのっとった結婚式のスタイルです。日本の結婚式は、もともと「祝言(しゅうげん)」という名で、家庭の床の間や神棚の前で行われていました。
それが明治33年、大正天皇が初めて日比谷大神宮で挙式されたのがきっかけとなって神前式が世の中に普及しました。そのため意外と歴史が浅いのです。
神前式では、祝詞奏上や三三九度、玉串奉奠(たまぐしほうてん)などの儀式が行われ、神様の前で結婚を誓います。
仏前式
仏前式は、寺院において仏様の前で結婚を誓います。仏前式は、全カップルのうち1〜2%と言われるため、ほとんど馴染みがないかもしれませんね。
いずれの寺院でも共通して読経や焼香などの儀式が行われますが、気になるのは宗派ではないでしょうか。
先祖代々お世話になってきた菩提寺があれば迷いがないかもしれませんが、両家が同じ宗派とも限りませんよね。その辺りは、事前によく話し合いを重ねて、意見を合わせる必要があるでしょう。寺院側は、宗派が違っても受け入れてくれるところが多いです。ただし、細かなルールは各寺院によってさまざまですから、挙式前に2人でよく話を聞いておくことが大切でしょう。
人前式

人前式は、形式にとらわれず、家族や友人の前で結婚を誓うスタイルです。白無垢に洋髪やアクセサリーを合わせるなど自由なコーディネートを楽しめます。ゲストとの距離が近く、アットホームな雰囲気で祝福を受けられます。
前撮りもおすすめ
実は、もっとも人気のある挙式スタイルは、教会式です。やはりウェディングドレスを着たいという花嫁さんが圧倒的に多いです。
この記事をお読みくださっている皆様の中にも、ウェディングドレスは外せない、という方が多いかもしれませんね。
そのような方におすすめなのが前撮りです。白無垢姿で挙式前に撮影して、記念に写真を残しておく方法です。彼にも紋付袴を着てもらって一緒に撮れば、ウェディングとは違った雰囲気が楽しめると思いますよ。
白無垢の選び方
続いて白無垢の選び方について解説しましょう。
ポイントは、素材と柄、そして生地の織り方、の3つです。
素材で選ぶ
白無垢の素材には、正絹、化繊、交織(こうしょく・まぜおり)などがあります。
正絹は高級感があり、美しい光沢が特徴です。化繊は比較的安価で扱いやすく、シワになりにくいのがメリット。交織は、正絹と化繊を混ぜたもので、両方の良い点を持ち合わせています。
正絹は、蚕の繭から作られた天然繊維で、独特の光沢と風合いが特徴。肌触りが良く、吸湿性や通気性にも優れています。しかし、デリケートな素材であるため、シミやシワになりやすく、お手入れに手間がかかります。価格も比較的高価ですよ。
化繊は、化学繊維のことで、ポリエステルやレーヨンなどがあります。正絹に比べて安価で、シワになりにくく、お手入れが簡単なのがメリットです。しかし、正絹の高級感や風合いには劣ります。
交織は、正絹と化繊を混ぜたもので、両方の良い点を持ち合わせています。正絹の風合いを残しつつ、化繊の扱いやすさを兼ね備えています。価格も正絹よりは安価です。
白無垢を選ぶ際には、素材の特徴を理解し、予算や好みに合わせるのがポイントです。
柄で選ぶ

白無垢には、鶴、亀、松竹梅など、縁起の良い吉祥文様が描かれていることが多いですよ。それぞれの柄には意味があり、夫婦円満や長寿、繁栄などの願いが込められています。柄の種類によって印象も変わるので、よく確認して選びましょう。
他にも、大輪の牡丹や椿、桜、菊、熨斗、鳳凰、宝尽くし、御所車など、さまざまなタイプがあります。こうしたデザインは、ウェディングにはない和装ならではの特徴で、伝統的なおもむきと選ぶ楽しみがありますよ。
織り方で選ぶ
白無垢の織り方には、緞子(どんす)、綸子(りんず)、縮緬(ちりめん)、錦織(にしきおり)などがあります。緞子は、光沢があり、重厚感のある織り方です。綸子は、柔らかく、しなやかな風合いが特徴です。縮緬は、シボと呼ばれる細かいシワがあり、独特の風合いがあります。
緞子は、経糸と緯糸を複雑に織り合わせることで、光沢のある模様を浮かび上がらせる織り方。重厚感があり、格式高い印象を与えます。
綸子は、経糸と緯糸を緩やかに織り合わせることで、柔らかく、しなやかな風合いを生み出す織り方です。光沢があって肌触りが良く、着心地が良いのが特徴です。上品で優しい印象を与えますよ。
縮緬は、経糸に強い撚りをかけることで、シボと呼ばれる細かいシワを作り出す織り方。独特の風合いがあり、着物によく用いられます。シワが目立ちにくく、お手入れが簡単なのがメリットです。
白無垢に合わせる髪型
ここからは、白無垢に合わせる髪型について解説しましょう。
白無垢の場合、伝統にしたがうなら髪型は和髪になりますが、最近ではそうしたルールにとらわれない風潮が強くなっています。むしろ和髪よりも洋髪がトレンドになりつつあるといっていいかもしれません。
髪型だけでなく、水引やリボンといった髪飾りでアレンジしたり、金箔やラメでさらに明るく華やかに演出したりする方たちもいますよ。
伝統に倣うなら「文金高島田」

伝統的なルールにしたがって挙式したい方には、「文金高島田」がおすすめです。
文金高島田は、江戸時代に未婚女性の中で流行した「島田髷(まげ)」の一種で、現在の形になったのは明治時代以降といわれています。
島田髷には、奴島田、投げ島田、つぶし島田、芸者島田など、さまざまな種類がありますが、中でも文金高島田は、髷の根を高い位置で結んだもっとも格が高いとされるスタイルです。
文金高島田は、トップの「髷」、「前髪」、両サイドの「鬢(びん)」、髷を折り曲げた後頭部の「いち」、うなじ部分でまとめた「たぼ」の5つのパーツからなります。
文金高島田では、角隠しを付けるか、綿帽子をかぶります。特にどちらでなければいけない、という決まりはなく、好きな方を選んで構いませんよ。ただし、角隠しは、色打掛や引き振袖に合わせても良いのですが、綿帽子は白無垢オンリーなので気をつけてくださいね。
また、綿帽子は、もともとはホコリ避けや防寒の目的で利用されていたアイテムのため、昔は神社や披露宴会場の屋内でかぶるのはルールに反していました。でも最近では、そこまでこだわることはなくなっているため、気にしなくても大丈夫ですよ。
角隠しは帯状の真っ白な布で、前髪を隠す様に鉢巻の要領で巻いて後ろで留めます。
綿帽子は、文金高島田の上からかぶるか、最近では洋髪でも頭頂部に綿帽子キーパーという専用器具を乗せて、その上からはぶる人たちが多くなっています。その方が楽ですし、お色直しでのアレンジもしやすいですからね。
文金高島田は、ロングヘアの方なら地毛で結えそうですが、ミディアムやショートの場合は、ちょっと難しそうですよね。
実は、文金高島田には、以下の3種類のセット方法があります。
- かつら
- 半かつら
- 地毛結い
文金高島田のかつらは、そのまますっぽりとかぶるだけのため、とても便利です。
時間もかからないので、当日の準備にも余裕がうまれるでしょう。お色直しでドレスを着る場合も、かつらをとってセットし直すだけで済むためラクでしょう。
前髪とサイドヘアを使って生え際を自然に見せるのが、半かつら。完全なかつらと違って、コンパクトにまとめられるのが特徴です。頭でっかちになるのがイヤという方は、こちらがおすすめですよ。
3つの中で一番自然に見えるのが、ご自分のヘアで結う地毛結いです。ロングヘアでなくとも肩くらいまで伸びていれば結える(理想は胸の辺り)ので、地毛でのセットを希望する場合は早めに美容師さんに相談してみるとよいですよ。
洋風アレンジもOK

最近では、洋風のヘアスタイルに綿帽子とか、綿帽子もかぶらずそのまま結婚式や披露宴に出る方が増えています。
おすすめは、以下の3つのスタイルです。
- アップスタイル
- ふんわり編み下ろし
- ゆるふわカールorハーフアップ
まずアップスタイル。白無垢に限らず、着物コーデでは、顔周りがスッキリと見えるアップスタイルが上品で見映えもします。
髪を結び、くるりんぱをし、毛先を入れ込むという3つのステップを基本に仕上げられるので、あまり難しくありません。
ロングヘアの方なら、後ろから首の横を通って、胸にかけてふんわりと編み下ろすのもオシャレですよ。少しカジュアル感が出ますが、リボンや水引、造花、生花などを使って華やかに飾ると、オリジナリティのある大人かわいいスタイルに仕上がりますよ。
最後にボブの場合は、無理にまとめようとせず、ゆるふわカールでナチュラルに仕上げるのもおすすめ。
ミディアムなら、耳の上で髪の毛をまとめて半分だけアップにするハーフアップもフェミニンでキュートな仕上がりになりますよ。
 | 白無垢のおしゃれな髪型は和髪?洋髪?伝統とトレンドのスタイル・花嫁の今どきヘアアレンジを紹介! 白無垢に合うおしゃれな髪型詳しく解説しています。髪飾りを使ったアレンジも紹介!合わせてご覧ください。 |
白無垢に合わせる小物
白無垢を着用する際には、さまざまな小物が必要です。それらを名称と共に簡単にご紹介しましょう。
掛下(かけした) | 白打掛のすぐ下に着用する振袖。成人式の振袖と違って、おはしょりを作らず裾を長めにし、あえて床にするように作られています。自然とゆったり、優雅に動くことになり、気品に満ちた独特の重みを感じさせます。 |
掛下帯 | 掛下の着付けに使う丸帯で、一般的なものより6〜8cmほど幅が狭いのが特徴。普通より高めのポイントで「文庫結び」にすると、白打掛を着たときの背中のラインがとても綺麗です。リボンのような見た目が特徴で四角い形が昔の「手文庫」という手紙や本を入れておく箱に似ていることから「文庫結び」と命名され、振袖や浴衣にも用いられます。 |
抱え帯(かかえおび) | 裾をする着物で外出する際に、裾をたく仕上げて固定するための細い帯。白無垢で外を歩くことはないため実用性はなく、装飾品の一種です。白打掛を羽織ると外からは見えません。 |
長襦袢(ながじゅばん) | 掛下の下に着る和服版の下着。汗や皮脂などの汚れ、着崩れ、寒さなどを防ぐ目的があります。 |
肌襦袢 | 長襦袢の下に着る下着で、掛下の汚れと着崩れ防止の役割があります。 |
腰紐 | 着崩れ防止やスタイルを良く見せるために腰に締める紐。 |
伊達締め | 長襦袢や掛下の衿合わせを安定させ着崩れを防ぐために伊達締めでしっかり固定します。 |
半衿 | 長襦袢に縫い付けたり、テープで留めたりして顔周りを華やかに見せるもので、汚れ防止の意味もあります。 |
重ね衿(伊達衿) | 掛下の衿の下に重ねるようにして何枚も着ているように見せるためのものです。 |
帯締め | 帯の着崩れを防止するために、帯のセンターに沿って上から巻く紐のこと。白無垢では中綿が入りボリューム感のある「丸くげ」を使います。 |
帯揚げ | 帯の内側に巻いて帯の形を整えたりズリ落ちないように安定させたりするためのもの。帯の上からチラ見せすることでコーデの一部としての役割も果たす。 |
帯板 | 帯を締める際に前面の内側に下敷きのように挟んで帯のシワを防止する「前板」と、帯の背面に下敷きのように挟み、帯の結びを美しく見せたりシワを防止したりするための「後板」があります。 |
帯枕 | 帯揚げの中に入れて帯結びを立体的に美しく仕上げるために使用します。 |
和装(打掛)ベルト | 白打掛の上前を下前に重ねてズレなくするための留めベルトです。 |
筥迫(はこせこ) | 元は、江戸時代に化粧ポーチの用途で使われていました。白無垢の際は掛下の衿と衿の間に挟むおしゃれアイテムです。 |
懐剣(かいけん) | 元々、身を守るために使われていた女性用の短剣で、魔除けの意味もあります。外から見えるようにして帯に差し込みます。 |
末広(すえひろ) | 末広がりを願う縁起物の扇子で、開いて使うことはありません。懐剣とともに外から見えるようにして帯に差し込みます。 |
足袋(たび) | 白無垢用の足袋は、かかとに付いたフックの「こばせ」が5枚(通常は4枚)のタイプを使用します。 |
草履 | 草履は高さがあるほど格が高いとされます。婚礼の際は高めがおすすめですが、転ばないように履きやすさも重視する必要があります。 |
白無垢の着付けはどうする?
白無垢をご自分だけで着付けるのは、まず無理と思っておいてください。
プロの着付け師にお願いして当日の朝に着付けてもらうのが一般的です。結婚式場によっては、白無垢や小物とセットで着付けもしてくれるケースが多いですよ。
着付けには、長ければ1時間半程度かかりますから、それまでにメイクや髪型を整えておく必要があります。その辺りも計算に入れて、当日は時間に余裕を持たせて行動してくださいね。
白無垢の手配はレンタルか購入

白無垢を手配する方法は、レンタルするか購入のどちらかになります。
それぞれにメリットがあるのですが、注意点もあるので解説しましょう。
レンタルのおすすめポイントと注意点
近年では、白無垢をレンタルする方が圧倒的に多いです。
理由は、コスパの良さと利便性の高さです。具体的には以下の通りです。
- 購入に比べてかなり安く借りられる
- 白無垢以外の小物もセットでレンタルできる
- ネットレンタルならスマホ一つで自宅にいながら手続きが完了し、白無垢の到着と返却が郵送で済む
- クリーニングが不要
- 多くの商品から好きなデザインを選べる
- 保管や虫干しなどのメンテナンスが不要
ただし、レンタル期間内に返却できない場合は、延滞料金がかかります。また、結婚式が多い春や秋シーズンは在庫が少なくなる恐れがあるため、早めの注文がおすすめです。
試着ができない点が心配かもしれませんが、サイト内のカタログの画像はかなり鮮明なうえ、サイズについても細かく説明されているので、届いてから期待していた感じと違ったと後悔することはほぼないでしょう。
購入のおすすめポイントと注意点
購入のメリットは以下の通りです。
- 生地やデザインを好みで選べる
- ジャストサイズに仕立てられる
- 着用前や後に時間を気にする必要がない
- 記念として残せる(将来お嬢様が着られる可能性も)
ただし購入の場合は、仕立てるまでに時間が必要なのと、レンタルに比べてかなりお金がかかります。小物もすべて自前で手配しなければなりません。もちろん有料です。また保管スペースが必要で、クリーニングやメンテナンスにも気を配らなければなりません。
白無垢の準備は早めがおすすめ!
既製品の場合は大丈夫ですが、白無垢をオーダーするなら長くて数ヶ月はかかります。生地を選んだり採寸したり、最後に家紋の刺繍を入れたり、と打ち合わせから購入手続きが完了するまでにはいくつもの手順があります。そのつもりで早めに購入手続きを済ませましょう。
また、レンタルもシーズンによっては品薄になるため、挙式の日程が決まったらできるだけ早くに予約するようにしてください。ショップにもよりますが、一年以上前からでも受け付けてくれるので、1日でも早く動くのがおすすめですよ。
まとめ

白無垢は、500年以上の歴史をもつ日本が誇る伝統的な婚礼衣装です。この国に生まれたからには、圧倒的な美しさと気品をそなえた白無垢にぜひ身を包んでいただきたいと思います。
白無垢は、単に見るのと実際に着用してみるのとでは、まったく違います。彼を始め、親御様などご家族の皆様、ご友人も喜んでくれるでしょうが、何よりあなたご自身が一番心満たされるに違いありません。人生の門出を祝うのにピッタリの白無垢をぜひご堪能ください!
e-きものレンタルでは、結婚式向けに、白無垢や色打掛、新郎向けの紋付袴、お母様やご親族の黒留袖・色留袖・訪問着などを幅広く取り揃えております。
愛知で創業50年以上、経験豊富なベテランスタッフが大切な婚礼準備を心を込めてサポートいたします。小物も無料でコーディネートしてお送りしますので、着物レンタルが初めての方もご安心ください。
皆様のご利用を心よりお待ち申し上げております。