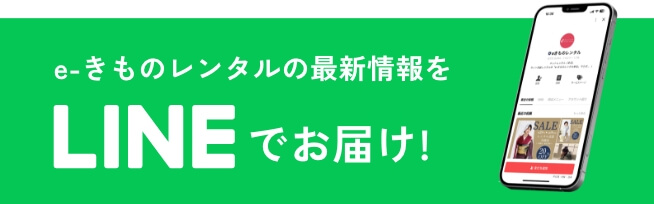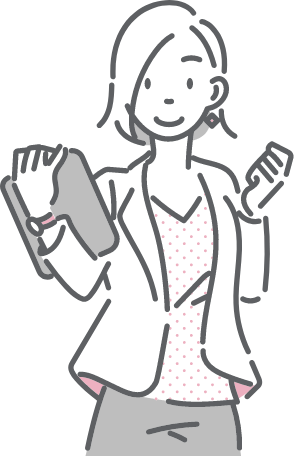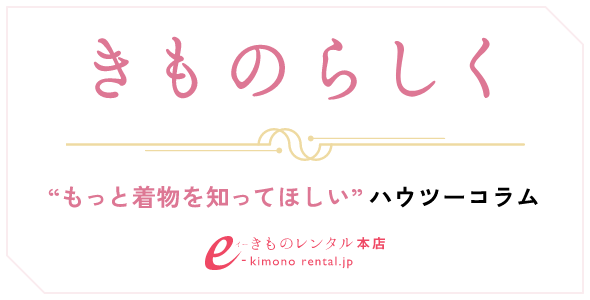
【和装の結婚式】色掛下とは?種類や選び方・おすすめのコーディネートを紹介!

【和装の結婚式】色掛下とは?種類や選び方・おすすめのコーディネートを紹介!
掛下というと、純白が基本です。白無垢の場合は打掛や掛下帯、その他の小物もすべて白いため、花嫁さんの清楚感や清潔感が引き立ちます。
色打掛の場合でも、掛下が白いことで打掛の華やかさとのコントラストがとても映えますよね。
ただ最近は、そんな掛下に色や柄が入った「色掛下(いろかけした)」がトレンドになりつつあります。
そこで今回は、色掛下が着用されるシーンや種類、選び方について解説します。色掛下について深く理解すると、婚礼衣装の選択肢がグンと広がりますよ。
これから結婚式準備にとり掛かる方や、婚礼衣装を何にしようかお迷いの皆様も、ぜひ参考にしてください。
色掛下(いろかけした)とは?

色掛下とは、婚礼衣装で身につける「掛下」の一種です。
掛下は、白無垢や色打掛を着用する際に、打掛のすぐ下に着る振袖を指します。
おはしょりはとらず、裾が床にするように長めに作られています。上に羽織る打掛も裾が長いので、動くときは自然とゆったり優雅になり、気品に満ちた独特の重みを感じさせるのが特徴です。
もともと掛下は、白無垢とセットで着用するもので、純白が基本でした。歴史的には、白無垢の後に色打掛が登場し、もとは白無垢が最高の格式で、色打掛はその下という位置付けでした。
しかし時代の流れの中で、最近では白無垢と色打掛が同じランクの第一礼装として扱われるようになっています。
それに伴って、白無垢や色打掛には白の掛下が常識だったのが、最近ではさまざまな色や柄の入った「色掛下」が登場し、見た目がドレッシーでオシャレであるのと新鮮さもあって徐々に着用されるケースが増えています。
色掛下はいつ使うの?
色掛下が使われるのは、神前式の結婚式や披露宴、またそれ以外の日に行う前撮りです。
色打掛が着用されるのは、以下の2パターンです。
- 白無垢の下に着る
- 色打掛の下に着る
もっともオーソドックスなパターンは、結婚式を白無垢にして、披露宴で色打掛にお色直しするというものです。
この場合は、打掛を白から色や柄のあるものに変えるだけのため、とてもラクです。髪型やその他の小物を変える必要もないので、披露宴の参列者を長時間待たせる心配もないでしょう。
ちなみに、白無垢は「これから嫁いで婚家の色に染まる」という意味があり、色打掛は「すでに婚家のお嫁さんになった」ことを意味します。
そのため先ほど述べた様に、順番としては白無垢の後が色打掛となります。一旦、色打掛を着用したら、その後に白無垢を着ることはルールとしてNGとなるので注意してくださいね。
色掛下でトレンドの挙式を楽しもう!
先ほど説明したように、掛下はもともと白一択でした。でも最近では、色掛下の占める割合が少しずつ増えています。
おそらく、これから結婚なさる方のお母様やお祖母様の時代は、白無垢はもちろん、色打掛でも掛下は「白」が当たり前。多くの場合、「掛下に色や柄が付いているなんて考えられなかった」とビックリなさるのではないでしょうか。
でも今は、色掛下がトレンドになりつつあるので、ご自分が気に入ったならあまり常識や風習にとらわれずに楽しむのもおすすめです。
色掛下は髪型や髪飾りも個性的!

伝統的なルールからいうと、白無垢や色打掛では、文金高島田に角隠しとか、綿帽子を被るのが一般的です。
でも色掛下になると、必ずしもそうではありませんよ。
色掛下はカラフルなものが多いですし、中にはレースがあしらわれた洋風のテイストを意識したタイプもあります。そのため、実際に着用してみると和に洋が融合したドレッシーな印象が強くなります。
そのため、とくに文金高島田に角隠しというスタイルはやや違和感があるでしょう。
それより、髪型はアップやハーフアップのシニヨンにして、胡蝶蘭やバラの生花や造花、ドライフラワー、水引、リボン、金箔・ラメ、ヘッドドレスなど髪飾りやヘアアクセサリーを工夫して華やかに仕上げる方が、トータルバランスが良くなりますよ。
前撮りもおすすめ!
とはいえ、白無垢に色掛下は周囲の目が気になるとか、伝統的なルールにしたがって挙式がしたいという方も少なくないでしょう。あるいは、挙式はウェディングにしたいという方もきっと多いはず。
そこでおすすめするのが、前撮りで色掛下を楽しんでしまうというものです。
前撮りなら、出来上がった写真を見るのは、ご自分や旦那さんを始めとしたお身内や親しい友達がほとんどでしょう。そのため、好きなコーデで気兼ねなく撮影してもらえますよ。
後でご紹介しますが、色掛下には、さまざまなカラーと柄があり、実際に見てみると想像以上に素敵です。きっと多くの皆様は、「一度着てみたい!」と思われることでしょう。
色掛下の種類

それではここから、色掛下にどのような種類があるのか、詳しく見ていきましょう。
無地
掛下の素材は、昔は正絹が基本でしたが、最近ではポリエステル製のものも増えており、その影響でさまざまなカラーの比較的お安い商品が数多く登場しています。
人気のある無地カラーには以下のようなものがあります。
- ライトピンク
- ライトブルー
- ライトグリーン
- クリーム
- ベージュ
- オレンジ
- イエロー
- パープル
- シルバー
- 濃いレッド
- ホワイト(白無垢で着用する白打掛とは異なり、白色をベースに刺繍などが入ったもののこと)
同じ色掛下でも、パステル系のものとシルバーや濃いレッドでは、ガラリと印象が違います。とくに色打掛の場合は、相性の悪い組み合わせにならないように気を配る必要があるでしょう。
柄もの
柄の入った色掛下には以下のようなものがあります。
- 七宝
- 市松模様
- 総絞り(生地を糸などで縛り、染料がしみこまない部分を作って染める手法。染まる部分と染まらない部分のコントラストが美しく、立体的に見えるのが特徴)
- 麻の葉
- 刺繍入り
無地のタイプに比べると、柄がある方が個性を演出できます。白無垢でも色打掛でも、柄があるとかなり目立ちますし、そこに人の目も集中しやすくなるので、人と被らないご自分だけのデザインにこだわりたい方にはおすすめです。
色掛下の選び方

色掛下を選ぶ際のポイントをご紹介しましょう。
似合うカラーを選ぶ
花嫁さんは、結婚式や披露宴では主役になりますし、一生の思い出にもなりますから、ご自分に似合うカラーの色掛下をチョイスするのが、基本です。
色白の方なら、ライトブルーやピンク、グリーンなどのパステル系、クリームなど明るめのものがよく似合います。
肌色が濃い目とか地黒の方は、シルバーやベージュ、オレンジ、濃いレッドなど、濃い色や落ち着いた色がおすすめですよ。
ただし、パステル系は膨張色のため、ふっくら体型の方は注意してください。気になる場合は、トーンの落ち着いた色の方がしっくりくるかもしれません。
季節を意識して選ぶ
婚礼衣装では季節感を意識することも大切です。
春シーズンであれば桜や梅、秋ならオレンジやブラウン系に紅葉の柄が入ったものも素敵ですよ。
色掛下のおすすめコーディネート
続いて、色掛下のおすすめコーデをご紹介しましょう。白無垢と色打掛に分けて解説します。
白無垢とのコーディネート
白無垢の場合は、打掛が万能性のある白ですから、掛下はどんな色や柄でも違和感なくマッチします。
例えば、濃い赤の無地や赤の総絞りなら、打掛の白とのコントラストがはっきりするため、結婚式らしいコーデになります。
また、ピンクやオレンジ、クリームは、明るくモダンなイメージが強くなります。ブルーやシルバー、グリーン、ベージュ、パープルなどは、しっとりと落ち着いた印象になりますよ。
ご自分がイメージする花嫁像にマッチする柄や色をうまくチョイスしてくださいね。
色打掛とのコーディネート
色打掛の場合、もっとも合わせやすいのは、同系統のカラーや柄の色掛下になります。
ピンク系やグリーン系などが、その代表例です。色打掛の柄の中からとくに目立つ色とマッチさせるのもよいでしょう。
小物も色掛下と合わせるとオシャレ度アップ!

白無垢や色打掛には、以下のような小物が必須です。
筥迫(はこせこ) | 元は、江戸時代に化粧ポーチの用途で使われていました。白無垢の際は掛下の衿と衿の間に挟むおしゃれアイテムです。 |
懐剣(かいけん) | 元々、身を守るために使われていた女性用の短剣で、魔除けの意味もあります。外から見えるようにして帯に差し込みます。 |
末広(すえひろ) | 末広がりを願う縁起物の扇子で、開いて使うことはありません。懐剣とともに外から見えるようにして帯に差し込みます。 |
白無垢の場合は、これらの小物も真っ白で統一するのが基本です。でも、色掛下の場合は、この3点の小物も、ピンクやブルーなど同じカラーで合わせると一気にオシャレ度がアップしますよ。ちょっとしたポイントではありますが、印象が大きく違ってくるのでおすすめです。
掛下帯と帯締めも大事なポイント!
掛下を着る際は、専用の掛下帯を使います。掛下帯は丸帯(帯生地を2つ折りにして筒状に縫い合わせた格式が最高の礼装に用いられる帯)で、一般的なものより6〜8cmほど幅が狭いのが特徴です。
普通より高めのポイントで「文庫結び」にすると、打掛を着たときの背中のラインがとても綺麗ですよ。リボンのような見た目が特徴で四角い形が昔の「手文庫」という手紙や本を入れておく箱に似ていることから「文庫結び」と命名され、振袖や浴衣にもよく使われます。
白無垢の場合は、掛下も掛下帯も白が基本ですが、色掛下になるとそうとも限りません。白をベースに金糸や銀糸があしらわれているものや、色掛下と同系色のタイプも数多くあります。
打掛に隠れてあまり目立ちませんが、掛下帯だけでなくその上から結ぶ帯締めもトータルで見るとコーデの大事なポイントになりますよ。
白無垢の場合は、掛下帯は打掛と同じ白にして、帯締めを色掛下と同じカラーに揃えると、全体的に締まりがあって映えます。
色打掛の場合も、同じく掛下帯を白にし、帯締めを色掛下や打掛のカラーと合わせると、とてもオシャレな仕上がりになりますよ。
こうした組み合わせは、普段のファッションにも通じるものがあります。ご自分に似合う色や好きな色をベースにして、「打掛×色掛下×掛下帯×帯締め」の配色や組み合わせを工夫してみてくださいね。
打掛コーデの仕組みを理解しよう!
ちなみにですが、打掛(白無垢も色打掛も)を着る順番は、「肌襦袢(もっとも肌に近い下着)→長襦袢(汗や皮脂汚れ、着崩れを防止する下着)→(色)掛下→打掛」となります。
打掛を着付けるには、先ほど説明した筥迫や末広、掛下帯、帯締め以外にも以下のような小物が必要になります。
腰紐 | 着崩れ防止やスタイルを良く見せるために、肌襦袢や長襦袢、掛下の着付けにあたり腰に締める紐。 |
伊達締め | 長襦袢や掛下の衿合わせを安定させ着崩れを防ぐために伊達締めでしっかり固定します。 |
半衿 | 長襦袢に縫い付けたり、テープで留めたりして顔周りを華やかに見せるもので、汚れ防止の意味もあります。 |
重ね衿(伊達衿) | 掛下の衿の下に重ねて何枚も着ているように見せるためのものです。 |
帯板 | 帯を締める際に前面の内側に下敷きのように挟んで帯のシワを防止する「前板」と、帯の背面に下敷きのように挟み、帯の結びを美しく見せたりシワを防止したりするための「後板」があります。 |
帯枕 | 帯揚げの中に入れて帯結びを立体的に美しく仕上げるために使用します。 |
和装(打掛)ベルト | 打掛の上前を下前に重ねてズレなくするための留めベルトです。 |
足袋(たび) | 打掛用の足袋は、かかとに付いたフックの「こばせ」が5枚(通常は4枚)のタイプを使用します。 |
草履 | 草履は高さがあるほど格が高いとされます。婚礼の際は高めがおすすめですが、転ばないように履きやすさも重視する必要があります |
まとめ

色掛下は、婚礼衣装としては昔にはなかったトレンドアイテムになります。そのため、実際に結婚式で着るとなると勇気がいるかもしれません。
でも、髪型も含めてとてもオシャレでモダンなコーデが楽しめるので、トライしてみる価値は大いにあるでしょう。
本番で着るのはちょっと・・・という方には、前撮りもおすすめですよ。
e-きものレンタルでは、結婚式向けに、白無垢や色打掛、新郎向けの紋付袴、お母様やご親族の黒留袖・色留袖・訪問着などを幅広く取り揃えております。
愛知で創業50年以上、経験豊富なベテランスタッフが大切な婚礼準備を心を込めてサポートいたします。小物も無料でコーディネートしてお送りしますので、着物レンタルが初めての方もご安心ください。
皆様のご利用を心よりお待ち申し上げております。